人生
ライフステージ別の生命保険の選び方も確認
ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里
マネーステップオフィス株式会社代表
人生の流れを年齢やライフイベントによって段階的に分けたものが、ライフステージです。ライフステージにかかわらず、万が一の死亡、病気・ケガ、働けなくなるなどのリスクを想定しておくことが大切です。しかし、いざというときの経済的な負担はライフステージによって異なる場合があるため、生命保険の選び方や必要保障額は変わることがあります。
更新日2025.11.19
掲載日2025.01.07

人生のリスクや備えておきたい生命保険は、ライフステージに応じて変わることがあります。各ライフステージにおいてどのようなライフイベントがあり、どれくらいのお金が必要なのかを知っておきましょう。また、各ライフステージで備えておきたい生命保険の選び方についても確認しましょう。
長い人生では、年齢や家族構成の変化、仕事や住まいの変化などに応じてライフスタイルが大きく変わることがあります。これらの節目を区切りとして、人生の流れを段階別に分けたものを「ライフステージ」と呼びます。
ライフステージは年齢とともに移り変わることもあれば、就職、結婚、出産、住宅購入や退職など、あるきっかけによって大きく転換することもあります。このようなイベントのことを「ライフイベント」といいます。
ライフイベントを迎えるときにはまとまった出費を伴ったり、ライフステージが変わると収入や支出の状況が変わったりすることがあります。このため、ライフイベントやライフステージの変化は、人生のお金の転換点にもなりえます。
一生のうちにどのようなライフステージやライフイベントを経験するかは、個人や家庭によって異なります。また、同じようなライフステージを歩んでいても、お金のかかり方には個人差があります。加えて社会環境の変化やライフスタイルの多様化といった影響を受ける場合もあるため一概にはいえませんが、主なライフステージ・ライフイベントに関わるお金の変化をまとめると、図のようなイメージになります。

では、各ライフステージにおける一般的な収入と支出の状況や、ライフイベントに伴う支出の平均額を挙げてみましょう。


・収入
就職して給与を受け取るようになると、定期的に収入を得るようになります。
・支出
家族とともに暮らす場合には、生活費などを自分の家計から支出しないこともありますが、一人暮らしをする場合には自分で生活費を支出するのが一般的です。
・主なライフイベントと支出
就職・転職
一人暮らし(始める場合):引っ越し費用、家具・家電・生活用品の購入費など


・収入
共働きの場合には、収入は夫婦2人分になります。このため独身の期間に比べて、世帯収入は高くなることがあります。
・支出
夫婦2人分の生活費がかかります。結婚前に双方が一人暮らしをしていた場合には、住居費や水道光熱費などは同居により各々で負担していた時期に比べて減ることがあります。
・主なライフイベントと支出
結婚:結婚費用、引っ越し費用、住宅購入費用など

出典:リクルートブライダル総研「ゼクシィ 結婚トレンド調査2024調べ」


・収入
勤続年数の増加やキャリア形成による昇給で、収入が増える場合もあります。一方、出産や子育てのための休業や時短勤務、転職や退職によって収入が減る場合もあります。共働きの場合には、収入は夫婦2人分になります。
・支出
夫婦の生活費に加え、子どもの生活費がかかるようになります。また、赤ちゃん用品や子ども用の家具、おもちゃといった子育てに関連する費用もかかり、夫婦2人の生活に比べて支出が増加する場合があります。
・主なライフイベントと支出

公的な補助制度はありますが、自然分娩の場合、2025年現在は分娩にかかる費用は公的医療保険の対象外で、入院費用なども含め、自己負担を伴う場合があります。子どもの誕生を機に自宅のリフォームや住み替えでお金がかかる場合もあります。

教育方針や地域などによる差がありますが、一般的には子どもが成長するにつれ教育費が増加する傾向があります。特に、大学などでの費用は高額です。

地域や立地、広さなどによって大幅な差があります。住居費の中心は家賃から住宅ローン返済に変わります。物件価格、住宅ローンの借入額、頭金を充てるかどうかなどの条件によって、購入時のコストや購入後の住居費支出にも差が生じます。住宅ローン控除や子育て支援制度など、負担を抑える制度もあります。
幼稚園から高校までにかかる学習費総額と大学でかかる教育費負担の合計額
(単位:万円)
table
高校までの進路 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 高校まで合計 | 大学 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
すべて公立 | 53.2 | 201.7 | 162.6 | 178.7 | 596.3 | 481.2 | 1,077.5 |
幼稚園だけ私立 | 103.8 | 201.7 | 162.6 | 178.7 | 646.9 | 481.2 | 1,128.1 |
高校だけ私立 | 53.2 | 201.7 | 162.6 | 307.7 | 725.3 | 481.2 | 1,206.5 |
幼稚園・高校が私立 | 103.8 | 201.7 | 162.6 | 307.7 | 775.9 | 481.2 | 1,257.1 |
小学校だけ公立 | 103.8 | 201.7 | 467.2 | 307.7 | 1,080.4 | 689.8 | 1,770.2 |
すべて私立 | 103.8 | 1,097.4 | 467.2 | 307.7 | 1,976.1 | 689.8 | 2,665.9 |
※幼稚園から高校までは学習費総額(学校教育費、学校給食費および学校外活動費の合計)、大学は入学費用と在学費用(4年間分)の合計額
出典:文部科学省「子供の学習費調査」(令和5年度)
日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果」をもとに筆者作成
住宅購入の所要資金の平均額
マンション | 5,592万円 |
土地付注文住宅 | 5,007万円 |
注文住宅 | 3,936万円 |
建売住宅 | 3,826万円 |
中古マンション | 3,033万円 |
中古戸建 | 2,573万円 |
出典:住宅金融支援機構「2024年度 フラット35利用者調査」より引用


・収入
子どもが独立する時期には、子どもが幼少の頃に比べ夫婦の年齢が上がっていきます。定年退職が近づくなどで給与水準が下がったり、早期退職や独立開業などで収入に大幅な変化を迎えたりする場合があります。
・支出
子どもが別生計になることで、生活費は減少傾向がみられます。
・主なライフイベントと支出
子どもの引っ越しや結婚(資金を援助する場合)


・収入
給与収入は減少するか、なくなる反面、会社員や公務員などの場合には、定年退職時に退職金収入を得られることがあります。65歳以降になると公的年金を受け取り始め、年金生活を迎えるケースが多いです。
・支出
夫婦のみ、または自分のみの生活費が中心になります。ただし、現役時代に比べて定期的な収入が少なくなるケースが多いため、それまでに準備した老後資金を取り崩して生活費に充てることがあります。また、病気やケガで医療費がかかる場合があります(原則70歳以上になると、所得などにより医療費の負担は1~2割に抑えられます)。介護が必要な状態になると介護費用がかかります(65歳以上の介護費用の負担割合は、原則1割です)。万が一の際には、葬儀費用がかかります。
・主なライフイベントと支出
リフォーム、親の介護費用、自分の介護費用、葬儀費用など

出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査 2024(令和6)年度」よりライフネット生命作成

筆者作成
葬儀の種類 | 葬儀費用の総額 |
|---|---|
家族葬 | 105.7万円 |
一般葬 | 161.3万円 |
一日葬 | 87.5万円 |
直葬・火葬式 | 42.8万円 |
※基本料金・飲食費・返礼品費の合計金額
出典:鎌倉新書「【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年)」より

このように、各ライフステージにおいては通常、収入や支出に特徴がみられます。また、ライフイベントを迎えると、日常生活に関わる収支の変化とは別にまとまったお金がかかることもあります。とりわけ「教育資金」「住宅資金」「老後資金」は人生の三大資金ともいわれ、ライフイベントの中でも特に高額なお金がかかる傾向があります。計画的に資金を準備するとともに、病気やケガ、死亡などで準備が難しくなったときへの備えを意識しておくことが大切です。
※挙げているライフステージは主な一例です。経験するライフステージの種類や回数、各ライフステージを迎える年代や順序は個々人によって異なります。
生きていくうえではライフステージにかかわらず、多かれ少なかれ病気やケガ、万が一の死亡といったリスクは共通して常に存在します。一方でそれらのリスクの大きさや備えておきたい保障額、備えの優先度などは、ライフステージによって変わることがあります。それはライフステージによって家族構成や収入・支出の状況が変わったり、受けられる公的保障制度が変わったりするためです。
そこで、ライフステージ別に、考えておきたいリスクや対応できる生命保険を考えてみましょう。


独身(単身)の時期に考えておきたいリスクには、自分の病気やケガ、万が一の死亡などが挙げられます。
start-pulldown
万が一のリスク
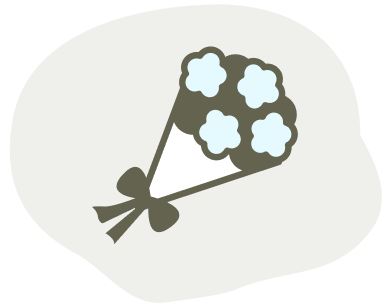
家族などを扶養するケースを除き、独身の時期に大きな死亡保障を準備する必要性はそれほど高くありません。ただし、自身に万が一のとき、葬儀代などを遺された両親や親族に負担させたくない場合には、死亡保障の生命保険を検討することがあります。この場合の必要保障額は、葬儀代を中心に想定し数百万円程度となるのが一般的です。
(該当する生命保険……定期死亡保険、終身死亡保険など)
end-pulldown
start-pulldown
病気やケガのリスク
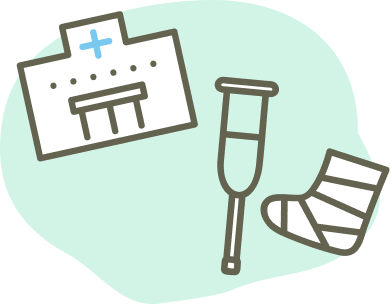
病気やケガで入院や手術をする、退院後に通院をするなどで、医療費がかかるリスクが考えられます。公的医療保険が適用される診療・治療では、医療費の自己負担割合は1~3割に抑えられます。また、自己負担額が一定を超えると負担が軽減される「高額療養費」などの制度もあります。
それでも、収入が少ない、貯蓄が少ないといった理由で、もし医療費の出費が発生したら負担に感じる場合や、医療費の全額が自己負担となる自費診療や先進医療、差額ベッド代などに備えたい場合などには、医療保障の生命保険を検討することがあります。がんや三大疾病など、特定の病気への備えを手厚くしたい場合には、それらに特化した保険も選択肢となるでしょう。
(該当する生命保険……定期医療保険、終身医療保険、定期がん保険、終身がん保険、特定疾病保障保険など)
end-pulldown
start-pulldown
働けなくなるリスク

病気やケガをしたときには、治療や療養のために仕事を休むことがあります。働き方や勤務先によっては有給休暇や傷病手当金など、仕事を休んだときに所定の日数まで収入が保障される制度を利用できますが、休業が長期間にわたる場合には収入が減少したり途絶えたりするリスクがあります。また、自営業やフリーランスとして働く場合にはこうした制度がなく、休業がすぐに収入減につながるリスクも考えられます。
入院や手術といった医療費とは別に、休業による収入減に備える生命保険を検討することがあります。
(該当する生命保険……就業不能保険など)
end-pulldown
start-pulldown
長生きのリスク

将来健康に長生きすると想定する場合には、ライフステージにかかわらず、老後資金を準備し始めることもあります。老後資金の積立てには貯蓄や資産運用などさまざまな手段がありますが、生命保険を活用する方法もあります。
(該当する生命保険……個人年金保険、養老保険など)
end-pulldown


夫婦2人暮らしで考えておきたいリスクには、自分やパートナーの病気やケガ、万が一の死亡などが挙げられます。
start-pulldown
万が一のリスク

夫婦どちらかが扶養されているか、共働きでそれぞれに収入があるか、遺族年金の受給対象となるかなどによって、死亡保障への考え方が異なります。万が一のとき、遺された相手に収入がない場合や遺族年金が支給されない、または不十分な場合には、葬儀費用やその後の生活資金の確保が難しくなるおそれがあります。そのようなリスクに備えて、死亡保障の生命保険を検討することがあります。
遺される側が老後を迎えるまでの生活資金全額を想定すると、年齢によっては必要な保障額が数千万円規模など高額になる傾向があります。一方で、遺される側に十分な収入や遺族年金、貯蓄を見込める場合には、高額な死亡保障は必ずしも要しません。この場合の必要保障額は、葬儀代を中心に数百万円程度となることもあります。
(該当する生命保険……定期死亡保険、終身死亡保険など)
end-pulldown
start-pulldown
病気やケガのリスク

病気やケガで入院や手術をする、退院後に通院をするなどで、医療費がかかるリスクが考えられます。公的医療保険が適用される診療・治療では、医療費の自己負担割合は1~3割に抑えられます。また、自己負担額が一定を超えると負担が軽減される「高額療養費」などの制度もあります。
それでも、収入が少ない、貯蓄が少ないといった理由で、もし医療費の出費が発生したら負担に感じる場合や、医療費の全額が自己負担となる自費診療や先進医療、差額ベッド代などに備えたい場合などには、医療保障を検討することがあります。がんや三大疾病など、特定の病気への備えを手厚くしたい場合には、それらに特化した保険も選択肢となるでしょう。
(該当する生命保険……定期医療保険、終身医療保険、定期がん保険、終身がん保険、特定疾病保障保険など)
end-pulldown
start-pulldown
働けなくなるリスク

病気やケガをしたときには、治療や療養のために仕事を休むことがあります。働き方や勤務先によっては有給休暇や傷病手当金など、仕事を休んだときに所定の日数まで収入が保障される制度を利用できますが、休業が長期間にわたる場合には収入が減少したり途絶えたりするリスクがあります。また、自営業やフリーランスなどとして働く場合にはこうした制度がなく、休業がすぐに収入減につながるリスクも考えられます。
もしも夫婦どちらかにこうした収入減少が生じた際に家計の維持が難しくなると考えられる場合、入院や手術といった医療費とは別に、休業による収入減に備える生命保険を検討することがあります。
(該当する生命保険……就業不能保険など)
end-pulldown
start-pulldown
長生きのリスク

将来健康に長生きすると想定する場合には、ライフステージにかかわらず、老後資金を準備し始めることもあります。老後資金の積立てには貯蓄や資産運用などさまざまな手段がありますが、生命保険を活用する方法もあります。
(該当する生命保険……個人年金保険、養老保険など)
end-pulldown


子どもの誕生後、夫婦と子どものいる暮らしで考えておきたいリスクには、自分やパートナーの病気やケガ、万が一の死亡などが挙げられます。
start-pulldown
万が一のリスク

夫婦どちらかが扶養されているか、共働きでそれぞれに収入があるか、遺族年金の受給対象となるか、子どもの年齢や人数などによって、死亡保障への考え方が異なります。万が一のとき、遺された相手に収入がない、遺族年金が不十分といった場合には、葬儀費用やその後の家族の生活資金・子どもの養育資金を確保することが難しくなるおそれがあります。そのようなリスクに備えて、死亡保障の生命保険を検討するのが一般的です。
遺された夫または妻が老後を迎えるまでの生活資金や教育資金の全額を想定すると、ほかのライフステージに比べて必要な保障額は高額になる傾向があります。子どもの人数や年齢などにもよりますが、死亡保障の必要保障額は数千万円規模になるのが一般的です。一方で、遺される夫または妻の収入や遺族年金を十分に見込める場合には、必要な死亡保障はそれほど高額にはならないケースもあります。
子どもの教育資金準備に対する備えとしては、学資保険やこども保険も選択肢の一つになります。これらは死亡保障と貯蓄性を兼ねており、万が一のことがなく無事に満期を迎えた際に活用することもできます。
(該当する生命保険……定期死亡保険、終身死亡保険、学資保険、こども保険など)
end-pulldown
start-pulldown
病気やケガのリスク

病気やケガで入院や手術をする、退院後に通院をするなどで、医療費がかかるリスクが考えられます。公的医療保険が適用される診療・治療では、医療費の自己負担割合は1~3割に抑えられます。また、自己負担額が一定を超えると負担が軽減される「高額療養費」などの制度もあります。子どもには、自治体の医療費助成制度によって医療費の自己負担の一部または全額が補助される地域もあります。
それでも、収入が少ない、貯蓄が少ないといった理由で、もし医療費の出費が発生したら負担に感じる場合や、医療費の全額が自己負担となる自費診療や先進医療、差額ベッド代に備えたい場合などには、医療保障の生命保険を検討することがあります。がんや三大疾病など、特定の病気への備えを手厚くしたい場合には、それらに特化した保険も選択肢となるでしょう。子どもがいる場合には、夫婦どちらかが入通院をする際には留守宅の家事や育児が負担になるケースもありますから、ベビーシッターや家事代行など、医療費以外の出費のリスクを想定しておくことも大切です。
(該当する生命保険……定期医療保険、終身医療保険、定期がん保険、終身がん保険、特定疾病保障保険など)
end-pulldown
start-pulldown
働けなくなるリスク

病気やケガをしたときには、治療や療養のために仕事を休むことがあります。働き方や勤務先によっては有給休暇や傷病手当金など、仕事を休んだときに所定の日数まで収入が保障される制度を利用できますが、休業が長期間にわたる場合には収入が減少したり途絶えたりするリスクがあります。また、自営業やフリーランスなどとして働く場合にはこうした制度がなく、休業がすぐに収入減につながるリスクも考えられます。
夫婦どちらかにこうした収入減少が生じたら家計の維持が難しくなると考えられる場合には、入院や手術といった医療費とは別に、休業による収入減に備える生命保険を検討することがあります。子どもがいる場合には収入減少が子どもを含め家族全体の生活に支障をきたすおそれもあるため、就業が不能になった際に支払われる給付金額を高めに設定することもあります。
(該当する生命保険……就業不能保険など)
end-pulldown
start-pulldown
長生きのリスク

将来健康に長生きすると想定する場合には、ライフステージにかかわらず、老後資金を準備し始めることもあります。老後資金の積立てには貯蓄や資産運用などさまざまな手段がありますが、生命保険を活用する方法もあります。
(該当する生命保険……個人年金保険、養老保険など)
end-pulldown


住宅ローンを借り入れて住宅を購入する場合には、万が一の死亡や病気などで返済が難しくなるリスクへの備えが重要です。そこで、住宅ローンの借入れの際には団体信用生命保険(団信)に加入することがほとんどです。
団信は一般的な生命保険とは仕組みが一部異なりますが、死亡保障(一部の商品は医療保障など)の役割を持っています。すでに十分な生命保険に契約しているうえに団信に加入すると、保障が重複したり、必要保障額に比べて保障額が過剰になったりする場合があります。
このため、住宅ローンの団信加入を機に、必要な生命保険の種類や保障額が変わることがあります。その場合には契約中の生命保険を見直し、保険金額の減額や一部解約などを検討します(住宅ローン契約前に生命保険に契約していなかった場合などは、団信に加入しても、万が一への保障が不十分な可能性もありえます)。


子どもが独立し夫婦のみで暮らす時期に挙げられるリスクには、自分やパートナーの病気やケガ、万が一の死亡などがあります。
start-pulldown
万が一のリスク

万が一のとき、遺された相手に収入がない、遺族年金が不十分といった場合には、葬儀費用やその後の生活資金の確保が難しくなるおそれがあります。そのようなリスクに備えて、生命保険で死亡保障を確保しておきたいものです。ただし独立した子どもと別生計になる場合には、子どもの生活費や教育費に対する保障は不要になります。このため死亡保障の保障額は、子育て期間中に比べると通常は大幅に低くなります。
(該当する生命保険……定期死亡保険、終身死亡保険など)
end-pulldown
start-pulldown
病気やケガのリスク

一方で、年齢が高くなると病気による入院・手術のリスクも比較的高くなります。また、転職や独立などにより、病気や長期療養の際に受けられる保障制度が変わることもありますので、医療費の負担や収入減少への備えを見直しておくことが大切です。
病気やケガで入院や手術をしたとき、公的医療保険が適用される診療・治療では、医療費の自己負担割合は1~3割に抑えられます。また、自己負担額が一定を超えると負担が軽減される「高額療養費」などの制度もあります。
それでも、収入が少ない、貯蓄が少ないといった理由で、もし医療費の出費が発生したら負担に感じる場合や、医療費の全額が自己負担となる自費診療や先進医療、差額ベッド代に備えたい場合などには、医療保障の生命保険を活用できます。がんや三大疾病など、特定の病気への備えを手厚くしたい場合には、それらに特化した保険も選択肢となるでしょう。
(該当する生命保険……定期医療保険、終身医療保険、定期がん保険、終身がん保険、特定疾病保障保険など)
end-pulldown
start-pulldown
長生きのリスク

将来健康に長生きすると想定する場合には、ライフステージにかかわらず、計画的に老後資金を準備することが大切です。老後資金の積立てには貯蓄や資産運用などさまざまな手段がありますが、生命保険を活用する方法もあります。子どもの独立後には老後が近づいてくるケースが多いですから、老後資金に充てる貯蓄が十分にあるかどうかを確認したうえで検討します。併せて、保険料が家計の負担にならないかも点検しておきましょう。
(該当する生命保険……個人年金保険、養老保険など)
end-pulldown


定年退職・リタイアをすると、収入の中心は一般的に年金となり、家計の状況は大きく変わります。また高齢期を迎え、病気やケガのリスクが一般的に高まります。こうした変化に対応できる老後資金が十分に備えられているかどうかにより、保険への考え方が異なります。
老後の生活費や病気・ケガの医療費、介護費用、万が一の死亡時の葬儀費用などを準備できる程度の資金があれば、生命保険の必要性はそれほど高いとはいえません。
start-pulldown
万が一のリスク

年齢を重ねるにつれ、万が一の死亡のリスクは高まります。葬儀費用に充てられる貯蓄が十分にない場合や、遺された家族に負担をさせたくない場合などには、死亡保障のある生命保険に契約しておくと、こうしたリスクに対応できます。一方で家族の生活資金については、高齢期には遺される夫または妻も年金生活である、子どもは独立して別生計であるなどで、生命保険による保障は不要なケースが少なくありません。このように、死亡保障の必要保障額は以前のライフステージに比べて低くなります。
なお、死亡保障の生命保険を検討する際に、持病の治療中である、病気やケガをしてから所定の期間を経過していないといった理由で標準的な生命保険への申込みが難しい場合には、健康状態に不安がある人向けの限定告知型(引受基準緩和型)や告知・診査のない無選択型の死亡保険も選択肢となるでしょう。
(該当する生命保険……定期死亡保険、終身死亡保険など)
end-pulldown
start-pulldown
病気やケガのリスク

高齢期には、病気やケガのリスクも高まります。公的医療保険が適用される診療・治療では、医療費の自己負担割合は所得や年齢などに応じて1~3割に抑えられます。また、自己負担額が一定を超えると負担が軽減される「高額療養費」などの制度もあります。
それでも、収入が少ない、貯蓄が少ないといった理由で、もし医療費の出費が発生したら負担に感じる場合や、医療費の全額が自己負担となる自費診療や先進医療、差額ベッド代などに備えたい場合などには、医療保障の生命保険を活用できます。がんや三大疾病など、特定の病気への備えに絞った保険もあります。また、持病の治療中である、病気やケガをしてから所定の期間を経過していないといった理由で標準的な医療保険などへ申込みが難しい場合には、限定告知型(引受基準緩和型)や無選択型のタイプも選択肢となるでしょう。
(該当する生命保険……定期医療保険、終身医療保険、定期がん保険、終身がん保険、特定疾病保障保険など)
end-pulldown
start-pulldown
介護・認知症のリスク

高齢になると、介護が必要な状態になったり、認知症になったりするリスクも高まります。公的介護保険の対象になる介護サービスの費用は、原則として自己負担割合が1割で、所定の自己負担額を超えると負担が軽減される「高額介護サービス費」などの制度もあります。それでも、介護サービスを受けるための初期費用や、公的介護保険の対象外となる介護サービスを受けるための費用負担が重くなると懸念する場合には、民間の介護保険や認知症保険を検討するケースもあります。
(該当する生命保険……民間の介護保険、認知症保険など)
end-pulldown
start-pulldown
相続発生時のリスク

万が一の死亡により遺された家族などが相続をする際には、遺産分割がスムーズに進まない、相続税の納税資金を十分に確保できないなどのリスクも考えられます。そのような事態に備えて、生命保険を活用することもできます。
(該当する生命保険……終身死亡保険、養老保険など)
ただし、上記で挙げた保険のいずれも、高齢期になると一般的には若い世代に比べて保険料が高めの傾向があります。持病や傷病歴があると、希望する保険に申し込めなかったり、契約はできても保険料が割増されたりなどの条件が付く場合もあります。また、限定告知型(引受基準緩和型)や無選択型など、持病のある人が申し込みやすい保険もありますが、これらは標準的な生命保険に比べて保険料が割高です。生命保険への契約や保有にあたっては、保険料の支出が老後の家計の負担にならないかを慎重に確認することが重要です。
end-pulldown
前述したように、ライフステージによって生命保険で備えておきたい保障の内容や金額は異なります。年齢を重ねたり、ライフイベントを迎えたりしてライフステージが変わるタイミングには、生命保険の見直しが必要かもしれません。
主に、次のようなタイミングはライフステージの転換点となり、生命保険を見直すことが多いです。各ライフステージにおいて、契約している保険がご自身やご家族のニーズに合っているかを確認し、過不足があれば見直しを検討してみましょう。その際、すでに契約している保険がある場合は、解約による不利益がないか、契約中の保険会社に確認しましょう。
生命保険を見直すタイミング・結婚したとき
・出産したとき、家族が増えたとき
・住宅を購入したとき
・定年退職をしたとき
など

ライフステージの転換によって、家族構成や家計収支、受けられる公的保障制度などが変わった場合には、生命保険の保障内容を点検するようにしましょう。契約中の保険で備えたいリスクに対応できそうなら、必ずしも見直しは必要ありません。保障内容に過不足があれば、見直しを検討しましょう。
いつ、どのようなライフステージ、ライフイベントを経験するかは、個人によって異なります。また同じライフステージでも、お金のかかり方やリスク、備えておきたい保障にも個人差があります。本稿の解説を参考に、ご自身やご家族に適した生命保険を取捨選択し、ニーズに合わせて保障額を検討しましょう。
ライフステージとは、人生の流れを就職や結婚、出産、住宅購入、退職などのライフイベントや年齢に応じて段階的に分けたものです。収入や支出の状況、家族の状況は、ライフステージによって通常は大きく変わります。教育費や住宅購入費など、特定のライフイベントではまとまった支出を伴うこともあります。ライフステージは個人によって異なるため、自身のライフイベントや必要な資金を把握し、適切な生命保険を選ぶことが必要です。また、ライフステージの転換点では生命保険の見直しを検討し、家族や家計の状況に合わせた保障を選ぶようにしましょう。
ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。
申し込みはオンラインで完結!