保険の基本
高額な医療費の負担を抑える公的制度とは
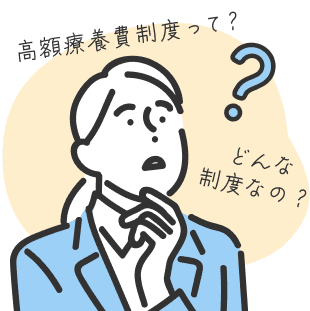
ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里
マネーステップオフィス株式会社代表
高額療養費制度は、医療費の自己負担が高額になった場合に支給される公的医療保険の仕組みです。1ヶ月に自己負担した医療費が所定の限度額を超えた場合に支給されます。対象になる医療費・対象外の医療費や、計算方法を確認しましょう。
更新日2024.11.26
掲載日2024.11.26
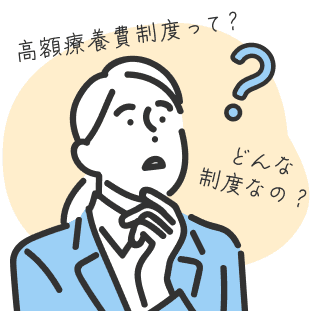

医療費の自己負担額が高額になった場合に利用できるのが、高額療養費制度です。公的医療保険制度では医療費の自己負担割合が1割~3割に抑えられていますが、1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が所定の限度額を超えた場合に、超えた金額が高額療養費として戻ってきます。公的医療保険が適用される医療費が対象で、保険適用外の自費診療や差額ベッド代などは対象外です。高額療養費制度の計算方法や申請方法などについて解説します。

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったときに支給を受けられる、公的医療保険制度の中の仕組みです。

公的医療保険が適用される治療や診療を受けた際には、医療費の自己負担割合は年齢や所得に応じて1割~3割に抑えられています(※)。病気やケガで医療費の自己負担額が高額になった場合に利用できるのが、高額療養費制度です。
※公的医療保険の自己負担割合
自己負担割合は、年齢や所得に応じて図のように定められています。

出典:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が、所定の限度額である「自己負担限度額」を超えたときに、超えた金額が「高額療養費」として戻ってきます。
加入している公的医療保険(会社員や公務員は勤務先の健康保険や協会けんぽ等、自営業者などは国民健康保険、75歳以上の人は後期高齢者医療制度)から支給されます。
しかし後から支給されるとはいえ、一時的には大きな負担となります。事前に手続きをしておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえることも可能です。事前申請に必要な手続きや申請書については、加入されている公的医療保険の保険者まで問い合わせてみましょう。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとにライフネット生命作成

高額療養費制度では、1ヶ月のあいだに窓口で負担した医療費が「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた部分の金額が「高額療養費」として払い戻されます。これにより、公的医療保険が適用される医療費のうち、実際に負担する医療費は「窓口での負担額―高額療養費」の額になります。
高額療養費を計算する際にはまず、公的医療保険が適用される医療費のうち、受診した個人ごと、医療機関ごとなどで、1ヶ月に窓口で自己負担した医療費の金額を合算します(69歳以下の人は、21,000円を超えた金額が対象になります)。合算した金額が所定の「自己負担限度額」を超えた場合に、高額療養費が支給されます。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとにライフネット生命作成


69歳以下の人の自己負担限度額は以下のとおりです。所得(年収)に応じて世帯ごとに設定されています。
Image Scroll

※会社員などで健康保険組合に加入している場合には、付加給付といって組合独自の自己負担限度額を設定しているところもあります。
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
例えば年収500万円の場合は、上記の表の「年収約370~約770万円」の適用区分に該当し、自己負担限度額は1ヶ月・世帯あたり「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」です。もし、医療機関の窓口で1ヶ月に負担した医療費の金額が30万円(10割で100万円)だった場合には、自己負担限度額は87,430円になります。30万円から87,430円を差し引いた212,570円は、高額療養費として支給されます。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとにライフネット生命作成


70歳以上の人の自己負担限度額も所得(年収)に応じて世帯ごとに設定されています。また、外来(通院)については個人ごとの限度額も設けられています。
Image Scroll

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとにライフネット生命作成
例えば、年収156万円~約370万円で一般区分にある所得水準の場合、自己負担限度額は1ヶ月・世帯あたり57,600円です。ただしこのうち外来での医療費が含まれる場合には、個人ごとに18,000円という限度額もあります。外来での窓口負担額が1ヶ月に18,000円を超えているかどうかを個人ごとに確認し、超えている場合には超えた金額が高額療養費として支給されます。また、18,000円以下の部分は入院や手術などの診療費と合わせて世帯ごとに合算され、自己負担限度額57,600円を超えていれば、超えた金額が高額療養費として支給されます。

高額療養費制度の対象になるのは、公的医療保険が適用される医療費です。

公的医療保険の適用対象となる医療費のうち、医療機関や薬局などで自己負担した金額が、高額療養費制度の対象になります。入院や手術、外来で、保険診療で受けた診療費や歯科の治療費、薬剤費などが対象です。

公的医療保険の適用がない自費診療や先進医療、入院時の食費負担や差額ベッド代などは、高額療養費制度の対象になりません。
そのほか、主に以下の費用は高額療養費の対象外です。
PC

SP

筆者作成
つまり病気やケガで入院や通院などをした場合、公的医療保険が適用される医療費の部分については自己負担割合が1~3割に抑えられ、所定の自己負担限度額を超えた場合には高額療養費も受給できるわけです。したがって、保険適用される医療費の大部分は実質的な負担が抑えられる可能性があるといえます。一方で、公的医療保険が適用されない医療費や差額ベッド代などは、原則として全額が自己負担となり、高額療養費の対象にもなりません。
Image Scroll

ライフネット生命作成
高額療養費制度が適用されたとしても差額ベッド代や先進医療などについては、全額自己負担となります。
こうした負担には、貯蓄や民間の医療保険などでの備えが重要です。

高額療養費制度で医療費の自己負担額を軽減するには、窓口で請求額を支払った後に払い戻しを受ける方法と、初めから医療費の請求額を自己負担限度額までに抑えてもらう方法があります。


病院など医療機関の窓口では請求された医療費をいったん支払い、自己負担限度額を超えたときに後から払い戻しを受ける場合には、自分で申請手続きをするのが基本です。
加入している公的医療保険所定の申請書を受け取り、必要事項を記入して提出や郵送をします。申請書には、診療を受けた日付や医療機関・薬局名、自己負担した金額、払い戻される高額療養費の振込先などを記入します。病院などの領収書の添付を求められる場合もあるようです。
会社員などで、加入している健康保険組合によっては、該当する月に高額療養費の支給を受けられることを教えてもらえたり、自分で申請手続きをしなくても高額療養費を計算して振り込んでもらえたりするところもあります。
手続きをすると、後日に高額療養費が指定の口座に振り込まれます。詳細は加入している公的医療保険によって異なりますが、支給までには受診月から3ヶ月程度かかることが多いようです。


医療費が高額になることがあらかじめ見込まれる場合には、医療機関での1ヶ月の請求額を自己負担限度額までに抑えてもらうこともできます。次の二つの方法があります。
受診前に、加入している公的医療保険で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」という書類を発行してもらい、受診時に医療機関に提示します。すると、1ヶ月の請求額は自己負担限度額までになり、それ以上の医療費がかかった場合でも請求はされません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録し(マイナ保険証)、受診時の本人確認に利用すると、限度額適用認定証などがなくても、医療費の請求額は自己負担限度額までに抑えられます。自己負担限度額を超えた医療費が発生した場合には、これを超える支払いは免除されます。マイナ保険証による本人確認に対応している医療機関を受診する場合に利用でき、かつ、事前にマイナ保険証の利用登録をしておくことが必要です。


高額療養費制度には、要件に該当した場合にさらに医療費の自己負担額を軽減する仕組みもあります。
直近12ヶ月に3回以上、同一世帯で高額療養費が支給された場合に、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる仕組みです。該当する場合には、1ヶ月の自己負担限度額は表のとおりになります。
Image Scroll

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
同じ月に1人で複数の医療機関を受診した場合や、同じ公的医療保険に加入する同一世帯の家族などが受診した場合に、それぞれが窓口で自己負担した医療費を1ヶ月単位で合算できる仕組みです※。
※69歳以下の人の受診は、21,000円以上の自己負担のみが合算対象です。
図表の例の場合、AさんとBさんが個人で自己負担した医療費は高額療養費制度の自己負担限度額に達しませんが、世帯で合算すると61,000円になります。世帯合算により自己負担限度額である57,600円を超え、超過した3,400円が高額療養費として支給されます。
PC

SP

※75歳以上、年収156万円~約370万円(自己負担限度額57,600円)、AさんとBさんが同一世帯の場合
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

はい。民間の生命保険や医療保険から保険金・給付金を受け取った場合にも、医療機関などで保険診療を受け、自己負担した医療費が1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費を受給することができます。
高額療養費は月の初めから終わりまでの医療費の自己負担額をもとに計算します。複数月にわたって入院した場合には、月ごとに申請手続きをします。医療費の自己負担額も月ごとに計算し、それぞれについて自己負担限度額を超える場合に、高額療養費が支給されます。医療費が同額でも、入院期間が同じ月内である場合と、月をまたぐ場合では支給される高額療養費の金額が変わる場合があります。
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合に支給される公的医療保険制度の仕組みです。1ヶ月にかかった医療費の自己負担の額が所定の自己負担限度額を超えた場合に、加入している公的医療保険から支給されます。対象になるのは公的医療保険が適用される医療費で、自費診療や差額ベッド代、食事代などは対象外です。高額療養費を受給する月が所定回数を超えた場合や、家族など同一世帯で同じ月に受診をした場合などには、さらに負担が軽減される仕組みもあります。
ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。
申し込みはオンラインで完結!