保険の基本
気になるライフステージ別の平均もご紹介
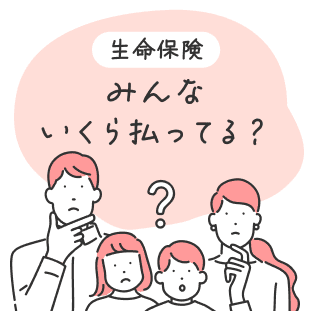
鈴木 さや子
株式会社ライフヴェーラ代表
生命保険の毎月の保険料、みんなはいくらくらい支払っているのか気になりますよね。必要な保障はご家庭によってさまざまです。家計の状況に応じた目安の金額を知り、ご自身の保険や家計を見直すきっかけにしましょう。
更新日2025.07.15
掲載日2025.07.15
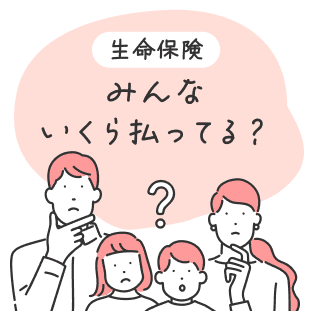

1世帯あたりの生命保険料の平均は、年間34.1万円です。年代別・ライフステージ別による水準の違いを知り、家計の状況に合った保険料の考え方を身につけることが大切です。


まずは世帯主の年齢別に、生命保険文化センターが行った調査から、どのくらいの保険料を支払っているかを確認してみましょう。このグラフは2012年と2024年の平均保険料の世帯主年齢別データを表しており、薄いオレンジのグラフが2012年、青いグラフが2024年のデータです。
img
![世帯年間払込保険料(全生保)[世帯主年齢別]。29歳以下:2012年:20.2万円、2024年:32.2万円。30~34歳:2012年:31万円、2024年:29.8万円。35~39歳:2012年:31.7万円、2024年:31.2万円。40~44歳:2012年:40.3万円、2024年:37.4万円。45~49歳:2012年:46.2万円、2024年:36.8万円。50~54歳:2012年:51.8万円、2024年:38.2万円。55~59歳:2012年:51.3万円、2024年:40.7万円。60~64歳:2012年:43.4万円、2024年:34.3万円。65~69歳:2012年:39.4万円、2024年:35.4万円。70~74歳:2012年:36.9万円、2024年:34.5万円。75~79歳:2012年:32.9万円、2024年:30.8万円。80~84歳:2012年:43.9万円、2024年:28.2万円。※85歳以上はサンプルが30未満のため割愛※全生保は民保(かんぽ生命を含む)、簡保、JA、県民共済・生協等を含む](https://mcms-images.lifenet-seimei.co.jp/assets/80b827524e754a219305ac66e62b49f1/3db15af860324fb8bb2d55d8bd9aa7da/article_YMD24_02_01.png?w=600&h=400)
出典:(公財)生命保険文化センター 2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」を基に筆者作成
上記データにおける、2024年の年間払込保険料の平均は34.1万円で、1世帯の平均は1ヶ月あたり約3万円弱です。
世帯主の年齢別に見ると、年間28.2万円から40.7万円と12.5万円の差がありますが、2012年のデータと比較すると、年代別の差は縮まっています。
平均払込保険料は、2012年の39.1万円から2024年には34.1万円へと、12年間で約5万円減少しました。特に45歳~59歳の年齢層では、約50万円から36.8万円~40.7万円に大きく減少しています。一方で、29歳以下の年齢層では20.2万円から32.2万円へと12万円増加しました。
このように、40歳以降の年齢層では2012年より平均払込保険料が減少している一方で、29歳以下では増加しているため、全体として年代別の差が縮まっているのです。


世帯年収に占める保険料の割合はどう変わってきているでしょうか。
img

出典:(公財)生命保険文化センター 2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」を基に筆者作成
この結果から、2024年では家計における保険料の割合は6.0%となっていることがわかります。
仮に年収400万円の世帯だと保険料は24万円、600万円の世帯なら36万円ですから、実際の年間払込保険料の平均である34.1万円と近いことがわかります。
次に、世帯年収に占める保険料の割合を、世帯年収別に調査したデータをご紹介します。
img

出典:(公財)生命保険文化センター 2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」を基に筆者作成
この調査結果を保険料の金額に引き直すと、200万円の14.4%は28.8万円、400万円の7.2%は28.8万円、600万円の5.8%は34.8万円、1,000万円の4.8%は48万円となり、年収が5倍になったとしても、保険にかけるお金が5倍になるわけではありません。年収が高いからといって、保険加入がそれだけ増えるわけではないことがわかります。
同じ年収でも、ご家族構成やライフステージによって保険以外の支出は大きく異なるもの。だからこそ、目安としての平均額を知ると同時に、自分に合った保障を得たうえで、保険料としても無理のない範囲に収めることが大切なのです。

同じ年齢でも、ライフステージは人それぞれです。ここでは、「結婚」と「子どもの誕生」というライフステージの変化によって、人はどのような不安を持つのかを見てみましょう。
img

出典:(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」を基に筆者作成
生命保険文化センターの調査によると、全世帯で不安に思っていることとして最も多い回答が「自分が病気や事故にあうこと(57.6%)」、次いで「家族の者が病気や事故にあうこと(50.0%)」となっています。

次に、結婚していない方と、子どもがいない夫婦世帯を比較してみましょう。
img

出典:(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」を基に筆者作成
未婚の世帯に比べ、既婚・子どもなしの世帯では、ほとんどの項目で経済的リスクを感じる方が増えています。自分の不慮の死による家族にかける負担、つまり死亡保障についても、結婚を機に意識する方が多いようです。

次に、「既婚・子どもなし世帯」と「既婚・末子未就学児世帯」を比べてみましょう。
img

出典:(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」を基に筆者作成
子どもの誕生によって、一段と経済的リスクを意識する方が増える様子がわかります。特に「家族の者が病気や事故にあうこと」が「自分が病気や事故にあうこと」よりも不安度が大きくなる点が特徴的です。
一方で、自分や配偶者の介護の心配や、老後の生活が経済的に苦しくなることなど、老後に関係する不安は減っています。
いずれにしても、結婚したときと子どもが生まれたタイミングは、ご自身の経済的リスクをあらためて考えるきっかけとなる可能性が高くなるといえます。

ライフステージの変化によって、皆さんが将来に対してどのような不安を持っているのかが分かりました。では、実際にライフステージ別にいくらぐらいの保険料を支払っているのかを見てみましょう。
img
![年間払込保険料(全生保・個人年金保険含む)[ライフステージ別]。未婚:16.5万円。既婚・子どもなし:19.6万円。既婚・末子未就学児:19.4万円。既婚・末子小学生:18.6万円。既婚・末子中学生、高校生:19.0万円。既婚・末子短大・大学・大学院生:20.9万円。](https://mcms-images.lifenet-seimei.co.jp/assets/80b827524e754a219305ac66e62b49f1/733054e143544bd485a0920f7796643c/article_YMD24_02_10.png?w=742&h=400)
出典:(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」を基に筆者作成
このグラフはライフステージ別に1人あたりの年間払込保険料を表したものです。未婚の方の16.5万円(月額約1.4万円)が一番少ないものの、最も多い「既婚・末子短大・大学・大学院生」の方の20.9万円(月額約1.7万円)との差は年間4.4万円ですから、それほど大きいわけではありません。どのライフステージであっても、保障の目的として「自分の病気やケガ」を心配されている方が多い点からしても、結婚や子どもの誕生を待たずとも、一定の保障を必要としている様子がわかります。
次に、1人あたりの年間払込保険料の金額帯別の割合を見てみましょう。
img
![年間払込保険料(全生保・個人年金保険含む)[ライフステージ別]。未婚:12万円未満:44.3%、12~24万円未満:26.4%、24~36万円未満:12.0%、36~48万円未満:3.2%、48~60万円未満:2.1%、60万円以上:3.8%。既婚・子どもなし:12万円未満:35.4%、12~24万円未満:29.6%、24~36万円未満:12.8%、36~48万円未満:6.6%、48~60万円未満:1.8%、60万円以上:4.0%。既婚・末子未就学児:12万円未満:34.4%、12~24万円未満:33.1%、24~36万円未満:13.5%、36~48万円未満:4.8%、48~60万円未満:2.1%、60万円以上:4.5%。既婚・末子小学生:12万円未満:33.6%、12~24万円未満:34.9%、24~36万円未満:15.0%、36~48万円未満:3.4%、48~60万円未満:2.8%、60万円以上:2.5%。既婚・末子中学生、高校生:12万円未満:33.5%、12~24万円未満:31.3%、24~36万円未満:17.3%、36~48万円未満:6.1%、48~60万円未満:1.9%、60万円以上:2.6%。既婚・末子短大・大学・大学院生:12万円未満:31.1%、12~24万円未満:29.8%、24~36万円未満:17.2%、36~48万円未満:6.6%、48~60万円未満:2.6%、60万円以上:4.0%。既婚・子どもすべて卒業(未婚):12万円未満:42.0%、12~24万円未満:28.6%、24~36万円未満:14.2%、36~48万円未満:3.8%、48~60万円未満:1.8%、60万円以上:2.9%。既婚・子どもすべて卒業(既婚):12万円未満:45.1%、12~24万円未満:30.7%、24~36万円未満:9.8%、36~48万円未満:4.0%、48~60万円未満:1.0%、60万円以上:2.9%。](https://mcms-images.lifenet-seimei.co.jp/assets/80b827524e754a219305ac66e62b49f1/76baf879833548299201b2d320083178/article_YMD24_02_11.png?w=516&h=800)
出典:(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」を基に筆者作成
このグラフでは、例えば「未婚」の方を見ると、年間払込保険料12万円未満の方の割合が44.3%と最も多いことがわかります。
そして、結婚を機に12万円未満の割合は35.4%に下がる一方、12~24万円未満の人が26.4%から29.6%に増加し、さらに子どもの誕生により、33.1%に増加しています。
「結婚」と「子どもの誕生」を機に保険を見直すようになり、その結果、払込保険料が増えていることが考えられます。

次に、ライフステージ別にみた生命保険加入率のデータを紹介します。民間の生命保険会社に加え、JA共済や県民共済・生協などの保障も含めた全生保の加入率です。
img
![生命保険・個人年金保険加入率(全生保)[ライフステージ別]。未婚:59.6%。既婚・子どもなし:81.7%。既婚・末子未就学児:89.3%。既婚・末子小学生:90.5%。既婚・末子中学生、高校生:90.6%。既婚・末子短大・大学・大学院生:91.6%。既婚・子どもすべて卒業(未婚):87.3%。既婚・子どもすべて卒業(既婚):83.6%。](https://mcms-images.lifenet-seimei.co.jp/assets/80b827524e754a219305ac66e62b49f1/d73465a360f045a393b805304d1f59bd/article_YMD24_02_13.png?w=591&h=400)
出典:(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」を基に筆者作成
ここでも、ライフステージの変化の中で最も加入率が上がるのは、結婚するタイミングです。未婚世帯の加入率59.6%が、既婚・子どもなし世帯は81.7%と20ポイント以上増加します。その後、子どもが生まれるタイミングでも加入率は上昇しますが、81.7%から89.3%とその差は大きくありません。最も加入率が高いのは、既婚・末子短大・大学・大学院生のステージですが、数字的には91.6%でほとんど差がない点も特徴といえそうです。


他の人がいくらくらい保険料を払っているか、どのくらい加入しているか、データをお伝えしましたが、一体いくらが良いのかは、世帯によって異なります。現実には毎月生活費がかかりますし、子どもが誕生すれば将来の教育費準備を始める必要も出てきます。また、住宅の購入という大きな支出を計画しているケースもあるでしょう。
ご自身の家計に無理のない範囲の保険料を考えましょう。


生命保険で準備する保障額は、自分が亡くなった際や入院などをした際に、どのくらいのお金が必要になるかを考えて割り出します。
準備する死亡保障は、「今後必要となる支出の総額」から「今後見込める収入の総額」と「すでに用意できている預貯金など」を差し引いた金額が目安となります。また、医療保障であれば、入院した際に必要なお金のうち、公的医療保険ではまかなえない自己負担の金額が目安となります。
死亡保険で準備しておきたいお金= 遺された家族に必要となるお金 - 入ってくるお金
医療保険で準備しておきたいお金= 入院した際に必要となるお金 - 公的医療保険からの給付
この中でも、特に死亡保障の金額は、家族構成などで大きく変わるため、結婚や子どもの誕生といったライフステージの変化に合わせて見直すことが大切なのです。
未婚であれば、「自分が亡くなったときにお金を遺すべき相手」がいないのが一般的なので、医療保障が中心となり、保険料もそれほど高くはならないでしょう。
結婚して夫婦共働きであれば、経済的に安定する可能性があるため、医療保険の他に葬式代ぐらいの死亡保障があれば良いかもしれません。ただし、住宅の購入を検討していて、「遺された家族のために住まいを残してあげたい」と考えるのであれば、住宅を取得するまでの期間限定で死亡保険に加入するのは、目的にかなっています。
そして、子どもが誕生すれば、わが子が社会人になるまでに必要なお金を遺してあげたいと考える方もいるでしょう。本格的な死亡保障を考えるタイミングには、子どもの独立までに必要な費用を考えることも大切です。
そのとき、どのようなお金をいくら遺しておきたいかを考えて、ライフステージが変わるタイミングで、都度見直すとよいですね。


保険料はなるべく安く抑えたい。でも必要な保障はしっかり確保したい。そう考える人が多いのではないでしょうか。そこで、保険料を抑えるコツをお伝えします。

同じ保障額でも、保険商品によって保険料は大きく異なります。養老保険や終身保険は貯蓄機能があることで、契約年齢や保障内容が同じ場合、定期保険に比べると高くなります。今は、NISAやiDeCoなど、将来の資産形成に利用できる積立制度が充実していますから、貯蓄と保障を切り分けることも大切です。保険料を低く抑えて、保障だけを準備したい場合は、定期保険の活用を検討しましょう。
※更新型の場合、更新日の保険料率に基づき、更新時の年齢で保険料が再計算されます。多くの場合、保険料が上がります。

保険料を抑えるために大切なのは、保険に入りすぎないことです。自分にとって必要な保障は何かをしっかり見極め、家計に合った保障額を維持するためにも、ライフステージに変化があったときは保険の見直しを忘れないようにしましょう。
※健康状態などにより、新たに保険に入り直すことができない場合があります。乗換による解約はお客さまの不利益になる場合がありますので、保険の見直しに当たってはご注意ください。

同じ保障額でも、保険会社によって保険料は異なります。特に定期死亡保険など保障内容がシンプルな保険こそ、保険会社を比較して選ぶことが大切です。ネット生保の生命保険は、ネット申し込みのため、人や店舗などにかかる費用が抑えられていて、比較的保険料が低い水準であることや、死亡保険のラインナップは定期保険が中心で見直しやすいことがメリットです。
生命保険の払込保険料には、絶対的な適正額はありません。今回の記事を基に、目安となる金額を知ったうえで、そのときの家計状況やライフステージに合う商品を選ぶようにしましょう。

生命保険は、年齢や性別ごとに過去の統計から想定される死亡する確率や入院する確率などを基に保険料が定められます。統計上は、若いときの方がそれらの確率が低いため、同じ保障内容であれば保険料は一般的に安くなります。
1度加入した保険契約の保険料は、期間満了まで変わりません。つまり、契約後に健康状態が悪化した場合でも、それを理由に保険料が上がることはありません。一方で、健康状態が悪化すると、新たに保険に加入することが困難なケースが出たり、加入できても保険料が割高となったりします。健康リスクは加齢とともに高まるものですから、必要性を感じたときにはなるべく早く加入することを検討しましょう。

統計上、1世帯あたりの年間払込保険料の平均は34.1万円、月額にすると約3万円弱です。また、1人あたりの年間払込保険料は、未婚の方で16.5万円(月額約1.4万円)、既婚かつ末子が短大・大学・大学院生の方で20.9万円(月額約1.7万円)ほどです。
ただし、これらの金額はライフステージによっても大きく異なります。ライフステージの変化に合わせて見直すことが重要といえるでしょう。
ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。
申し込みはオンラインで完結!